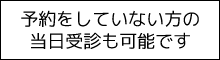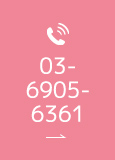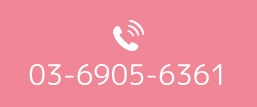子宮頸がんに関して
子宮頸がんは20〜30代の女性が罹患するがんの中で最も多く、近年30〜40代の女性で増加しています。子宮頸がんはヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルス感染者が原因と判明しており、つまりこのHPV感染を予防することで子宮頸がんの予防につながります。
がんリスクの高いHPVの型と予防方法
HPVの型は数多く存在するのですが、中でもHPV16型と18型の発症率が高いとされており、日本人の場合は子宮頸がんを発症した60〜70%の方に同タイプのHPVが認められています。残りの30〜40%には他の方のHPVが関与しており、特に31型・33型・35型・45型・52型・58型は子宮頸がんの発症リスクが高いとされています。 子宮頸がんワクチンとはこれらのがん発症リスクの高い型のHPV感染を防止することで、子宮頸がんの発症する可能性を減少させるワクチンです。 現在、日本国内で採用されている子宮頸がんワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類がありますが、2021年に発売された9価ワクチンであるシルガード9が最も子宮頸がんの発症リスクを抑える効果の高いワクチンとなります。現在における世界の子宮頸がんワクチンの主流はシルガード9です。ただし現在の日本において、シルガード9の接種に関しては公費助成はなく自費診療での接種となります。 NOBUヘルシーライフ内科クリニックでは、子宮頸がんワクチンとして最も効果が高いシルガード9の接種を承ります。合計3回の接種で終生免疫を得ることが出来ます。
接種対象者
- 当クリニックでは15歳以上の方への接種を行なっています。
- 未成年者の方は保護者の方の同伴が必要です。
接種方法とスケジュール
- 筋肉注射を合計3回接種します。
(通常2回目は初回接種から2ヶ月後、3回目は初回接種から6ヶ月後です)
- まずWEBかお電話で予約をお願い致します
- 接種前問診や診察を行います
- 接種に問題がないと判断されましたらワクチン接種を行います
副作用とリスクに関して
注射部位の痛みや腫れや発熱などの副反応が生じる可能性がありますが、他の様々なワクチンと比較して発生しやすいということはありません。重大な副作用としてはアナフィラキシー、ギランバレー症候群、急性散在性脳脊髄炎、複合性局所疼痛症候群の報告がありますが、発生頻度が不明な程に極めて稀と言えますし、このような重大な副作用報告とHPVワクチンとの因果関係を示す根拠は報告されていません。
料金
※シルガード9は合計3回の接種が必要です。
※他院で接種歴ある方も当クリニックで接種対応しますが、その際はこれまでの接種記録をご持参ください。
※接種希望の方は以下より問診票を印刷し記載して持参をお願い致します。
| シルガード9 (接種1回分) |
28,000円 (税込・診察料金込) |
|---|
予約について
WEB予約またはお電話にて予約を承っております。
※予約を受けてからワクチン発注します
(在庫確保の為、約1週間前には予約をお願い致します)
※ワクチンは保存期間が限られているため、受診キャンセルの際には前日までに必ず『お電話』ください。事前連絡なしにキャンセルされた場合は、次回接種をお断りする場合がありますのでご了承ください。
(一部キャンセルをお受けできないワクチンが存在します)
HPVワクチン接種に関するよくある質問
接種スケジュール途中で妊娠した場合は?
シルガード9以外の他のHPVワクチン含め妊婦への接種は安全性が確立していませんので推奨されません。具体的には下記のように行動してください。
- 1回目接種後に妊娠が判明した場合→出産後に2回目及び3回目接種
- 2回目接種後に妊娠が判明した場合→出産後に3回目接種
途中から別のHPVワクチンへの変更は可能か?
他のHPVワクチンとの互換性に関して安全性や有効性を評価した報告は現在のところありませんので同じワクチンの3回接種を勧めます。
過去に他のHPVワクチンの3回接種を完了しているが、追加でシルガード9の接種は可能か?
海外の診療ガイドラインではHPVワクチン接種完了者にシルガード9の追加接種は推奨されていませんが、接種不適合者には該当しないためシルガード9の接種自体は可能です。
検診で子宮頸がんが見つかった場合でもHPVワクチン接種は可能か?
ワクチン接種自体は可能ですが、HPVワクチン一般として既に感染しているHPVを除去したり、既に発生しているHPV疾患の進行抑制効果はありません。ただしHPVには様々な型が存在するので、シルガード9のような多価ワクチンを接種することで、現在感染していないHPV型の新たな感染や病気の発生を予防することは可能です。