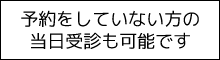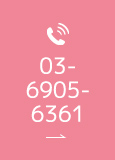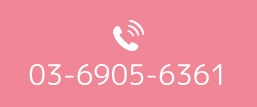糖尿病で腎機能低下するのはなぜ?糖尿病性腎症とは
糖尿病とは
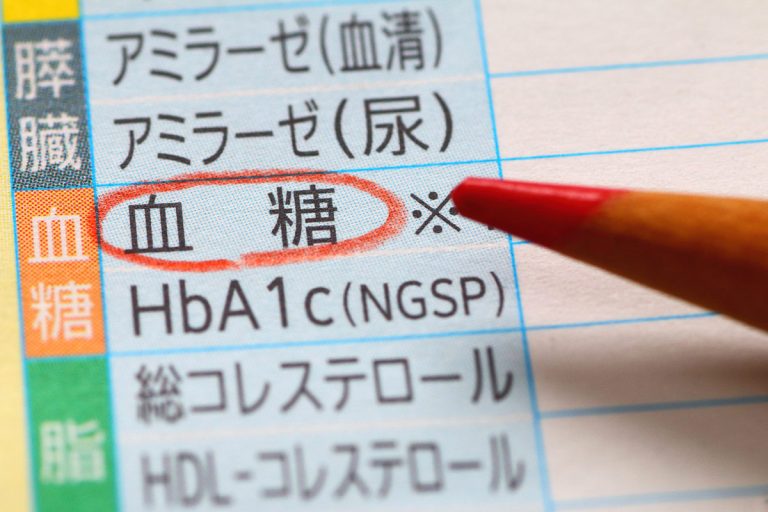 糖尿病は、血糖値が慢性的に高くなる病気で、主にインスリンの分泌不足や働きの低下が原因で発症します。インスリンは膵臓から分泌され、血糖を細胞に取り込みエネルギーとして利用する役割を持っています。しかし、インスリンの分泌が不足したり、十分に働かなくなると、血液中の糖が過剰に増え、全身にさまざまな影響を及ぼします。
糖尿病は、血糖値が慢性的に高くなる病気で、主にインスリンの分泌不足や働きの低下が原因で発症します。インスリンは膵臓から分泌され、血糖を細胞に取り込みエネルギーとして利用する役割を持っています。しかし、インスリンの分泌が不足したり、十分に働かなくなると、血液中の糖が過剰に増え、全身にさまざまな影響を及ぼします。
糖尿病には2つのタイプがあります。1型糖尿病は、免疫の異常によって膵臓の細胞が破壊され、インスリンがほとんど作られなくなる状態です。一方、2型糖尿病は、インスリンの分泌が不十分だったり、体内で適切に作用しないことで血糖値が高くなります。
1型糖尿病は自己免疫の異常や遺伝的要因が関係しており予防が難しいのですが、2型糖尿病の主な原因として、食べ過ぎ、運動不足、ストレス、加齢などが影響します。
糖尿病による合併症
血糖値が高いと、血液中の糖が血管の内壁に蓄積し、血管が硬くなったり、詰まりやすくなります。その結果、合併症が発生しやすくなります。
なかでも「糖尿病神経障害」「糖尿病網膜症」「糖尿病性腎症」の3つは三大合併症と呼ばれ、血糖管理を適切に行わない場合、ほぼ確実に発症するとされています。
糖尿病性腎症とは
 糖尿病性腎症は、糖尿病による高血糖が腎臓の機能を低下させる合併症の一つです。
糖尿病性腎症は、糖尿病による高血糖が腎臓の機能を低下させる合併症の一つです。
腎臓には約100万個の糸球体(血液をろ過する微細な毛細血管の集合体)が存在し、これにより老廃物を排出し、体内のバランスを維持しています。しかし、高血糖状態が続くと、血液中の糖が血管の内壁に蓄積し、糸球体の血管が厚く硬くなることでろ過機能が低下し、老廃物を適切に排出できなくなります。また、高血糖を排出しようとするため、糸球体が過剰にろ過を行い長期間負担がかかる事で糸球体が疲弊し、糸球体の血管が詰まりやすくなります。
その結果、本来は体に必要なタンパク質が尿中に漏れ出すようになり(蛋白尿)、腎臓のろ過機能が乱れます。さらに病状が進むと、糸球体が破壊され、老廃物や余分な水分を十分に排出できなくなり、高血圧、むくみ、貧血などの症状が現れ、尿毒症の発症リスクも高まります。
糖尿病性腎症の症状
糖尿病性腎症は、ある程度進行するまで自覚症状が現れにくい病気です。しかし、発症すると尿中に本来含まれないはずのアルブミン(尿蛋白)が排出されるようになります。この状態を放置すると、腎臓のろ過機能が低下し、余分な水分や老廃物が血液内に蓄積。その結果、全身のむくみ、倦怠感、貧血といった症状が現れ、日常生活に影響を及ぼします。
糖尿病性腎症進行のステージ
第1期(腎症前期)
自覚症状はなく、腎機能も正常。
第2期(早期腎症期)
尿に微量のアルブミンが漏れ始める(微量アルブミン尿)。※自覚症状なし
第3期(顕性腎症期)
尿中の蛋白量が増加し、むくみ、高血圧を発症します。
第4期(腎不全期)
腎機能が著しく低下し、老廃物が蓄積(尿毒症)し、体がだるい、食欲不振、吐き気、集中力低下、口臭(アンモニア臭) などの症状が出ます。
また、体内の水分が排出できなくなると尿量が減少し、むくみ(浮腫)が発生(顔や足が腫れる)。
肺や腹部に水が溜まり、呼吸困難や腹部膨満感が生じます(肺水腫・腹水)。
第5期(透析期)
腎機能がほぼ失われ、生命維持のため透析や腎移植が必要になります。
糖尿病性腎症の主な原因
糖尿病性腎症は、糖尿病による高血糖が長期間続くことで腎臓の糸球体が損傷し、腎機能が低下することが主な原因です。具体的な原因は以下の通りです。
高血糖による腎臓の血管障害
腎臓には糸球体と呼ばれる細かい網の目状の血管の塊があり、血液をろ過する働きを担っています。しかし、高血糖の状態が続くと、余分な糖が血管の内側に蓄積し、糸球体の血管が次第に厚くなり、硬くなることで、ろ過機能が衰え老廃物の排出が適切に行えなくなります。
糸球体の過剰な働きと負担の増大
血糖値が高いと、腎臓は余分な糖を排出しようとして糸球体が過剰に働き続けることになります。この状態が長く続き負担がかかることによって、糸球体の血管が傷つき、尿にタンパク質(アルブミン)が漏れ出すようになります。漏れたタンパク質が血液中の糖と結びつき、糸球体の網の目を詰まらせる原因になり、腎機能の悪化を招きます。
高血圧による腎臓への負担と悪循環
高血圧は糸球体の血流が過剰になり、血管に負担がかかる事によって血管を傷つけ、ろ過機能がさらに低下します。ろ過機能が低下すると腎臓は機能を維持するため血流が必要となりもっと血液を流さねばと、血圧を上昇させる働きをします。これにより高血圧を悪化させ、腎機能が急激に低下するという悪循環に陥ります。
糖尿病性腎症の治療
 糖尿病性腎症の治療は、進行を遅らせ、腎機能を維持することが目的です。病期に応じた適切な対応が重要で、主に以下の方法があります。
糖尿病性腎症の治療は、進行を遅らせ、腎機能を維持することが目的です。病期に応じた適切な対応が重要で、主に以下の方法があります。
血糖コントロール
血糖値を適切に管理することで、腎臓への負担を減らし、病状の進行を抑えます。
治療方法
食事療法、運動療法、薬物療法
血圧管理
高血圧は腎機能低下を加速させるため、適切にコントロールすることが重要です。
血圧目標
130/80mmHg未満(腎機能が低下している場合)
治療方法
降圧薬を使用し、塩分制限、運動療法を実施
蛋白尿の抑制
蛋白尿の増加は腎機能の悪化につながるため、早期に抑えることが大切です。
治療方法
高血圧の予防に加え、薬物療法
食事療法
腎臓への負担を軽減するため、栄養バランスを考えた食事制限が必要です。
塩分
1日6g未満(高血圧予防)
タンパク質
腎機能に応じて制限(進行した場合0.6~0.8g/kg/日)
カリウム・リン
腎機能低下が進んだ場合、過剰摂取を避ける
禁煙・運動療法
禁煙
喫煙は血管障害を悪化させるため、必ず中止
運動
適度な運動(ウォーキングなど)で血流を改善
透析・腎移植(末期腎不全の場合)
腎機能が著しく低下(eGFR 10mL/min未満)すると、透析療法(血液透析・腹膜透析)や腎移植が必要になります。
早期発見のために定期的な検査が重要
糖尿病性腎症の進行を防ぐには、早期の診断が欠かせません。自覚症状が現れる前の段階から定期的に尿検査を行うことで、尿中のアルブミンがわずかに増え始める「微量アルブミン尿」の時点で腎症を発見できます。さらに、腎症と診断される前から、血糖や血圧を適切に管理することが腎機能の悪化を防ぐために重要です。